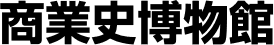サークルセンター刊行物
『あしたづ』執筆者索引
『あしたづ』創刊号から第22号までの執筆者索引(五十音順 敬称略)
▶部分をクリックして頂くと、一覧が開きます。あ行
執筆者名
号数
目 次
あ
青井 建之
13
東大阪市の橋 道と川から橋を探る
青木 貴美子
1
木村長門守重成
青ぶどう俳句会
10
俳句5句
青ぶどう俳句会
11
俳句10句
青ぶどう俳句会
12
俳句10句
明尾 圭造
15
絵筆を持った郷土史家 堤楢次郎
浅野 詠子
12
『河内文化のおもちゃ箱』と記憶遺産
足代 健二郎
10
「日羅」についての覚え書き
足代 健二郎
11
「猪飼野ゆかり著名人番付」覚え書き
足代 健二郎
12
王仁博士「難波津の歌」 万葉仮名・和文・ハングル 歌碑建立までの覚え書(前段)
足代 健二郎
13
「難波古図」についての覚え書き
足代 健二郎
14
キョンチャル(警察)アパート探索の顛末
足代 健二郎
15
祇園牛頭天王ノート
足代 健二郎
17
私見 磐船明神社の近世・近代史(前編)
足代 健二郎
18
私見 磐船明神社の近世・近代史(後編)
足代 健二郎
19
「伊加賀」「伊賀ケ(いかが)」地名から物部氏を考える
足代 健二郎
20
八尾における「神武・聖徳太子・家康」伝説の関係
足代 健二郎
21
「仏滅紀年」「宝篋印塔」に関するメモ
足代 健二郎
22
外環沿い・布市町鯨骨出土地一件の顛末
天竹 薫信
1
山岳信仰と陀羅尼助丸考
天竹 薫信
4
「壱岐島の元冦」一考
天竹 薫信
6
多武峯にあるアンラ樹について
天竹 薫信
8
古都を廃墟から救ったウォーナー伝説再顧
天竹 薫信
9
田辺聖子氏の色紙のはなし―おくのほそ道の曽良の句に想う―
天竹 薫信
10
花登筺氏の「一日図書館長」-付・司馬遼太郎氏のことなど-
天竹 薫信
12
楠氏正成の桜井宿で子息正行に教訓の壁書
天竹 薫信
13
「特甲幹」という名の私の戦塵記-鬼の天伯・地獄の高師一朝の夢-
天竹 薫信
15
北陸路・親不知子不知の渚に佇みて
有木 靖
3
《弘川寺『西行消息』にみる》西行法師の執念
い
伊ヶ崎 淑彦
1
愛しのナガスネヒコと河内地名考
伊ヶ崎 淑彦
2
水辺と夢のムラ そして司馬さん
伊ヶ崎 淑彦
3
東大阪ロマンの寺
伊ヶ崎 淑彦
4
石器ねつ造事件"から学ぶもの―その背景と事件を追う―
伊ヶ崎 淑彦
5
知られざる河内木綿の謎をさぐる―人こそ歴史・小島勝治を鏡として―
伊ヶ崎 淑彦
6
歴史再見"お水取りや磐井の乱を問い返す
伊ヶ崎 淑彦
7
大和川は文化始源の地なり―東大阪 いろは 独案内―
伊ヶ崎 淑彦
8
騎馬民族がやってきた―五世紀の紀伊・泉南から―
伊ヶ崎 淑彦
9
郷土史・独案内 謎解き歴史散歩―吉田を歩く―
伊ヶ崎 淑彦
10
「知られざる飛鳥へ」
伊ヶ崎 淑彦
11
出雲神話のウラ世界(抄)-イツモ王国とヤマトー
伊ヶ崎 淑彦
12
河内の柳田国男といわれた小島勝治
伊ヶ崎 淑彦
12
活動弁士ひとすじ 浜 星波
伊ヶ崎 淑彦
12
扶桑国論 -紀伊・上天野にみつけた-
伊ヶ崎 淑彦
13
称徳女帝と道鏡法師考 -得をしたのは誰か-
伊ヶ崎 淑彦
14
郷土史・異説あれこれ
池田 治司
21
平成30年度秋季企画展「はかりの文化史」を終えて
石河 亮平
21
「いにしえの由義寺跡から」学ぶ 一三〇〇年前 日本の中心は八尾だった
石上 敏
18
三〇周年記念事業参画の記
石田 郁代
6
―紅き花みな友にゆずりて―山川登美子と与謝野晶子
石田 郁代
7
堺のひと・与謝野晶子の歌 新大和川河口のまちを詠む
石田 郁代
8
戦後六十年、学徒動員の追憶の集い 十五歳の思い出
伊藤 俊夫
14
回想の片山長三
伊藤 俊夫
15
四條畷高校美術準備室 -続・回想の片山長三 -
伊藤 俊夫
16
回想の片山長三③ 「古美術と初期絵画」
稲国 与那夫
22
令和元年三題記~内助淵大蛇伝説の一件ほか~
井上 伸一
9
新田会所の通説を考え直す
井上 法子
15
きものと私
今村 與志雄
14
十三仏碑見てある記
今村 與志雄
15
住道からぶらり中垣内越え宝山寺への道
岩下 梅野
1
もんじと共に
岩永 憲一郎
1
「富景楼」をめぐる古文書と漢詩
岩永 憲一郎
3
高安山を越えて来た人びと
岩永 憲一郎
5
幕末の志士学者 飯田忠彦の弁明
岩橋 初子
1
生駒 山ふところのいぶし銀
う
植田 啓司
4
飛田家の大工道具
内倉 武久
18
古代の「天皇」は福岡県に都していた
内倉 武久
19
崇神天皇と太田多根子と熊襲
内倉 武久
20
関西における熊襲と紀氏族の足跡―よくよく見ると「それだらけ」―
内倉 武久
21
神功皇后は佐賀の山中で生まれ、みやこ町に葬られた謎の"女性天皇"~解明に新資料~
内倉 武久
22
福岡県赤村に超巨大古墳前方後円墳形、安閑天皇御陵の可能性も
梅田 豪
19
近畿日本鉄道 鶴橋運河側線
梅田 豪
20
近鉄奈良線(瓢簞山~石切)「大軌」境界標
うらら短歌会
18
短歌
うらら短歌会
20
河内を詠む
お
太田 理
3
盾津(たてつ)の飛行場
太田 理
15
盾津飛行場と私とその周辺
太田 理
16
点描・田原の民俗-傍示さし・砂絵
太田 理
17
点描・田原の民俗その二ー地域の人々の信仰・習俗
太田 理
18
点描・田原の民俗その三ー大和と河内の田原の民俗
大西 英利
2
東大阪市域に遺る 六十六部廻国供養の石造物
大西 英利
5
中河内に遺る大坂相撲頭取鏡山代々と其の墓碑
大西 英利
18
明治前期、河内の相撲の一面
大西 英利
20
河内に遺る大坂勧進大相撲の力士碑
大東 道雄
2
「澁川郡 大地村 文書より」幕末の村事情"庄屋役をめぐって"
大東 道雄
3
古代、橘島余話"「横野ノ堤と並河誠所」
大東 道雄
6
堺 中百舌鳥"「筒井家 屋敷を訪ねて」
大東 道雄
7
新大和川筋 水論一件
大東 道雄
10
長州征伐と村人達-渋川郡大地村文書より-
大東 道雄
11
古代橘島余話(二)『祖父間は邑智島』"四天王寺御手印縁起の謎を解く"
大東 道雄
13
河内の治水「田輪ノ樋、余聞」安宿郡国分村文書より
大東 道雄
14
河内の伝説ものがたり
大東 道雄
15
万葉歌に顕れた、河内の風景
大東 道雄
22
伊勢本街道踏山記
岡本 好行
16
ヒアリングによる記録
小川 秀人
22
枚岡神社ものがたり
荻田 昭次
1
クスノキ
荻田 昭次
3
池島・泉證寺の蓮如上人六字名号
荻田 昭次
4
歴史教科書を考える
荻田 昭次
5
鰭付円筒埴輪について
荻田 昭次
6
畿内の寺塔探訪
荻田 昭次
7
大和川付替三題
荻田 昭次
8
戦後六十年
荻田 昭次
9
与謝野晶子・鉄幹の東京時代
荻田 昭次
10
帝国キネマと東大阪
荻田 昭次
12
若江で戦った木村重成
奥田 哲郎
1
生誕百周年 欲も得もない不思議な郷土偉人 安岡正篤
小野 賢一
13
大正・昭和の鶴橋、河内を愛した文画人・堤梨雪
小野 賢一
15
楢次郎の描く「大正期の鶴橋」を読み解く
小野 賢一
20
「大正期から昭和初期の鶴橋町形成史」研究ノート(1)―鶴橋耕地整理事業・平野川改修と方面委員制度の検討を通して―
小野 賢一
21
昭和初期・鶴橋町域の下層民衆のくらしを探る鶴橋町形成史研究ノート(3)-方面委員会・1932年救護法前後から1936年国家的機関化期の検討ー
か行
執筆者名
号数
目 次
か
甲斐 駿一郎
6
鴻池新田会所の石造物
甲斐 駿一郎
7
鴻池新田開発に心血を注いだ鴻池善右衛門宗利
海谷 寛
3
松永久秀、あれやこれや
海谷 寛
8
旅が紡いだ旅
海谷 寛
9
小説ノート「幻の城」
海谷 寛
10
風景抄
海谷 寛
11
残月抄
海谷 寛
14
近古摺譚
勝田 邦夫
3
中河内の十三仏
加藤 弘子
3
創作「お糸はん」
川口 哲秀
1
府史跡河内往生院伝承地
川口 哲秀
2
東高野街道(東大阪市内)往生院六萬寺
川口 哲秀
7
渡辺橋
川口 哲秀
8
楠木正行・正時を掘起す
川口 哲秀
9
東大阪市内に残る楠木氏銅像・石像
川口 哲秀
10
楠木父子子別れの人形
き
北山 良
11
往馬大社火まつりのこと
北山 良
14
戦時中の楠風荘
木村 余里
3
西園寺公達"道君"幻の御入院
木村 直規
21
「土器造りから見えてくる信仰心と現代世界」
京嶋 覚
14
摂津と河内-二つの百済-
く
楠田 有子
13
木綿の産地を訪ねて
久保下 多美子
19
鸕野讃良(持統天皇)~倭国から日本への画期の時代に生きたウノノサララは中大兄の娘か?~
黒田 収
5
大和川付け替えと二人の大商人―河村瑞賢と鴻池宗利―
黒田 収
7
大和川付け替えと勘定奉行 荻原重秀
黒田 収
8
三ノ瀬公園の歴史
黒田 収
10
「行基を考える」
黒田 収
13
小阪物語
黒田 収
14
布施の話
黒田 収
15
俊徳道・十三街道
こ
工場を記録する会
(旧 町工場を記録する会)17
町工場主の歩みから見た『河内、この百年』第四期
工場を記録する会
(旧 町工場を記録する会)19
モノづくり長寿企業ストーリー 株式会社河内製綱所 東大阪市衣摺三丁目
古作 登
19
「関西の棋士いまむかし」
小谷 一生
5
楠木正勝の伝説 その一
小谷 一生
6
楠木正勝の伝説 その二
小林 ひろみ
13
太宰治著 『女生徒』を読んで
小林 義孝
9
河内だいとうの成り立ち
小林 義孝
10
まちの風格をつくるー平野屋新田会所保存の一歩先―
小林 義孝
11
聞き書き 船場商人銭屋の『細雪』
小林 義孝
13
住道だより-河内の歴史あれこれ-
小林 義孝
14
わが町で最高の学術と芸術を-住道だより(その二)-
小林 義孝
15
三十五年間の夢-住道だより(その三)-
小林 義孝
16
住道だより(その四)
さ行
執筆者名
号数
目 次
さ
斉藤 正治
2
『良弁杉にまつわる子安明神の由来』
坂上 弘子
4
恩智川の「橋」「端」
坂上 弘子
19
恩智神社、わからへんこと
桜井 伝次郎
1
歴代組
佐々木 裕子
2
消えいく式内社
佐藤 啓二
14
三野郷のことなど
佐藤 啓二
17
昭和11年の布施町 25人が死亡した氷菓食中毒
佐藤 啓二
18
ひとのみち事件の中、「大布施市」へ 昭和11~12年の布施
佐野 一雄
2
天王寺まいり
佐野 一雄
3
御本山道"追想
佐野 一雄
4
花山法皇 入覚叡信
佐野 一雄
5
壺坂峠
佐野 一雄
6
秋の夜話
佐野 一雄
7
へたごろ"の詩
佐野 一雄
8
へたごろの詩
佐野 一雄
9
泣くな新兵さん
佐野 一雄
10
鬼と兵隊
佐野 一雄
11
東高野街道杖ついて
佐野 一雄
11
かわちアラカルト「川柳7句」ほか
佐野 一雄
12
「帝キネ」が燃えたァー
佐野 一雄
12
東高野街道 杖ついて
佐野 一雄
13
東高野街道 杖ついて
佐野 一雄
14
東高野街道 杖ついて
佐野 一雄
15
東高野街道 杖ついて
佐野 一雄
16
東高野街道 杖ついて
佐野 一雄
(佐野 智雲)17
河内の茶粥
佐野 一雄
(佐野 智雲)19
読書の楽しみ
澤田 平
22
怪僧 弓削道鏡と今東光
し
志田 宣博
18
私とジャズ
品川 清
10
地形図から見る二世紀から五世紀の吉備王国―楯築と造山から『記・紀』伝承のウラ側へー
品川 清
19
津軽半島・最古の水田稲作遺跡から徐福集団渡来の真実性を知る
清水 守民
21
ずらされた「藤原京」天武に背いた持統の企み
清水 守民
22
海から来た大王 百舌鳥・古市古墳群の謎を解く
す
杉山 三記雄
1
大坂夏の陣・古戦場幻の"若江堤"を追って
杉山 三記雄
2
「巨麻郷」を歩いて
杉山 三記雄
4
船板塀に魅せられて
杉山 三記雄
5
大和川付替工事竣工三〇〇周年を前にして
杉山 三記雄
6
街の"観光力"アップしよう
杉山 三記雄
7
大和川から"ルソン"へ 末吉孫左衛門の活躍
杉山 三記雄
8
ロスアンジェルス・ソウル・上海~三都物語
杉山 三記雄
9
『狐は人をだますの?』
杉山 三記雄
10
遅咲き"広沢瓢右衛門
杉山 三記雄
11
没一〇年 米之助師匠を想う
杉山 三記雄
12
漫才の祖 玉子屋円辰
杉山 三記雄
13
美女堂氏遺愛碣と若江
杉山 三記雄
14
若江の忠霊塔-わが父の眠れるところ-
杉山 三記雄
15
わが故郷の若江
杉山 三記雄
16
旧大和川跡は丸ごと"史跡"なり
杉山 三記雄
17
戦後70年、「若江の忠霊塔」の調査を終えて
杉山 三記雄
18
生駒山西麓に息づく文学と人の交遊
杉山 三記雄
19
英国初代公使オールコックと暗越奈良街道
杉山 三記雄
20
治水翁・大橋房太郎と河内
杉山 三記雄
21
絵でつづる小阪の移ろい
杉山 三記雄
22
八戸ノ里の歴史を想う
せ
関谷 広
5
河内三大馬場の中の玉櫛松の馬場
関谷 広
6
大阪空襲
関谷 広
7
大和川付替と築留の歩み
関谷 広
12
伴林光平
せきれい短歌会
10
短歌5句
せきれい短歌会
11
短歌10句
せきれい短歌会
12
短歌10首
た行
執筆者名
号数
目 次
た
高井 晧
6
智識寺跡出土の葡萄唐草紋鴟尾
高井 晧
7
七・八世紀の旧大和川水運
高井 晧
11
古代交通都市の中心である鳥坂寺跡の歴史的重要性ー国「史跡」指定に向けてー
高井 晧
12
智識寺の廬舎那佛は金銅佛であった
滝住 光二
1
元河内若江寺にあった重文の涅槃図を加茂町常念寺で発見するまで
滝住 光二
2
史跡見学と歴史の裏側を探る
滝住 光二
3
楠木正行の五ケ所の墓について
滝住 光二
4
続楠木正行の墓と父正成の墓について
滝住 光二
5
北前船復元白山丸訪問記
滝住 光二
6
観世流の創始者 観阿弥と世阿弥のたどった生涯
滝住 光二
7
大和川付替と中甚兵衛の功績を記念して―中地区市史編纂を訴える―
滝住 光二
8
遣唐使井真成と河内直鯨について
田中 郁夫
14
近代産業の始まりと鐘紡住道工場
田中 絹子
2
芭蕉翁の句碑を尋ねて
田中 絹子
4
北京門礅(メンドル)に触れて
田中 絹子
7
古墳の都 新羅王朝一千年の古都慶州を訪ねて
田中 絹子
9
義経ドリームロード
田中 絹子
11
アムール河畔の岩絵(ペトログリフ)を尋ねて
田中 絹子
22
第三十四回 中河内拓本展を終えて
田中 まり(他二名)
3
『父性の復権』を読んで
棚橋 利光
4
二つの太平記
棚橋 利光
7
築留樋組の成立
棚橋 利光
7
付替え三〇〇年と高安城を探る会三〇年
玉元 早枝子
11
コットン・ボールに魅せられて
ち
曺 奎通
16
生野区(大阪市)を核とする周辺地域の塩化ビニールレザー小史
つ
槌間 博
3
一期一会
槌間 博
4
歩く旅 四国遍路日記から
槌間 博
5
歩く旅 続四国遍路日記から
槌間 博
6
歩く旅 伊豆下田街道
津田 悟
14
ダムに浮いた岐阜県徳山村の「ふるさとの碑」拓本
津田 悟
15
野崎観音の 梵鐘銘文拓本
津田 悟
16
東高野街道道標つれづれ
堤 條治
15
祖父・堤楢次郎の思い出
と
飛田 太一郎
7
大和川の付替と今・昔―両岸歩いて、歴史をのぞいた―
富永 美代子
2
手作り本に心よせて
な行
執筆者名
号数
目 次
な
中井 由榮
3
日本一周旅紀行
中井 由榮
6
釈尊の足跡をたどる―インド聖地を旅して―
中井 由榮
7
日下のホタル ―ホタルの川づくりによせて―
中井 由榮
9
木綿の育んだ河内平野―河内木綿 コットン・クラブ 創立によせて―
中井 由榮
10
佐渡島紀行―悠久の国仲平野―
中井 由榮
11
もんじ(文字)が伝えるものー父が残した戦争の記憶ー
中井 由榮
13
一枚の絵
中井 由榮
14
日下のほたるⅡ 蛍雪の光
中井 由榮
15
河内木綿雑記
中井 由榮
16
文字の形が持つ魅力
中井 由榮
18
「石切参道・アラカルト」
中井 由榮
19
石切参道・アラカルト Ⅱ
中井 由榮
20
『日下村 石工 小平次』
中井 由榮
22
河内木綿再生への道
中尾 智行
21
「弥生分銅」の発見
中河内拓本クラブ
16
西高野街道・里程石をたずねて
中河内拓本クラブ
21
久宝寺寺内町と御幸森天神宮を訪ねて
中谷 作次
2
新聞でみる「河内のニュース」
中谷 作次
3
神武天皇御東行における浪速の上陸地 ―生駒山西麓―『孔舎衙村』昭和十五年の回顧
中谷 作次
5
随筆
中野 善典
16
鶴橋のプロレスラー・高泰文の風景
中野 善典
18
生野区は映画館の町だった
中野 善典
19
大阪での非公式試合 力道山と三ノ瀬公園の謎
中野 善典
21
住宅地図の世界 千日前を散策する
中野 善典
22
堺筋の百貨店にみる栄枯盛衰
成瀬 俊彦
18
東大阪市内製造業 長寿企業の経営実態調査
成瀬 俊彦
19
東大阪市観光振興とモノづくり~既存施設の活性化と工場ミュージアム構想~
成瀬 俊彦
21
綿作の起源と河内木綿関連産業の盛衰
成瀬 俊彦
22
金属の起源と河内鋳物の勃興・盛衰
に
西川 禎昭
5
流し節 正調河内音頭と常光寺
ね
根川 章子
11
「源氏物語私文」一 -女三宮の出家についてー
根川 章子
12
「源氏物語私文」二 -六条御息所の類型表現について-
根川 章子
13
「源氏物語私文」三 -女君たちの競演-
根川 章子
14
「源氏物語私文」四 -姫君たちの結婚 玉鬘の大君の場合-
根川 章子
15
「源氏物語私文」五 -垣い間見二題 紫の上と女三宮 -
根川 章子
16
「源氏物語私文」六 -花散里に見られる類型表現について-
根川 章子
18
「源氏物語私文」七 -六条院の女君と四季-
は行
執筆者名
号数
目 次
は
初谷 勇
14
街道ブランド・コミュニティへの歩み-『暗越奈良街道2012』ガイドブック初公刊-
浜田 昭子
2
六枚の神社の棟札と文献・古文書に見る善根寺春日神社檜皮葺二十五人衆「檜皮御座」の二九六年間にわたる活動
浜田 昭子
4
善根寺春日神社檜皮葺大工について
浜田 昭子
5
善根寺春日神社檜皮葺大工について―その近世の活動と実態―
浜田 昭子
9
森長右衛門が語る「二百八十年前の河内の暮らし」―吉宗の日光御社参と疱瘡―
浜田 昭子
10
河内の村と人々「村定めと人々の暮らし」-支配者と御百姓―
ひ
樋口 須賀子
15
彦根・宗安寺の血染めのすすき ~木村長門守重成公首塚の由来~
樋口 須賀子
19
大阪商人と近代大阪、文化~ズンゾと辿る商いの道~
樋口 須賀子
20
朝鮮通信使絵画とコレクション~ズンゾと辿る朝鮮街道の祭り~
平嶋 述司
7
「大和川の付け替え」を考えながら
ふ
福田 太郎(他一名)
1
「五十村峠」について
福田 太郎
2
かしわら 郷土史かるた
福田 太郎
4
チベット駆け足の旅
福元 匡代
2
黒板とチョーク
福元 匡代
3
あなたならどっち!
福元 匡代
5
竜笛
福元 匡代
6
榎大明神
福元 匡代
7
忘れもの
藤井 広治
14
創作『甦れ!福やん』
藤井 広治
15
晩秋-シリーズ「まちづくり」(1)-
藤谷 久美子(他二名)
3
『父性の復権』を読んで
藤本 優子(他二名)
3
『父性の復権』を読んで
藤本 優子
5
国木田独歩と基督教 再論
藤本 優子
6
文学作品に見る人間の真相―選ぶということ、自由に生きるとは―
藤本 優子
7
遠藤周作が世に問うたことと聖書的視点からの問題点(『海と毒薬』『悲しみの歌』より)
藤本 優子
8
『リア王』は悲劇か―リアの生涯を考える―
藤本 優子
9
私にとって書くということ
藤本 優子
10
私の忘れられぬ人―西口孝四郎氏との出会いー
ま行
執筆者名
号数
目 次
ま
政 和美
4
楠 正行の奮戦と終焉について
政野 敦子
1
垣間みた下小坂村とその周辺
政野 敦子
2
安政大地震と津浪
政野 敦子
4
大塩平八郎の乱と河内
政野 敦子
7
〈史料紹介〉大和川古川筋等新田大積り帳
桝谷 政則
12
柘植葛城
桝谷 政則
13
柏原鉄道物語
桝谷 政則
15
「高井田山古墳」の被葬者は誰なのか
松井 紀子
5
鎌倉幕府と楠木氏―楠木氏御家人説について―
松浦 哲朗
19
うらら短歌会の楽しみ
松浦 利弘
18
随想 「私と万葉集」
松浦 利弘
20
考察 難波の歴史と万葉の時代―横野万葉歌の風土、その時期と作者
松浦 利弘
21
紫草(むらさき)の万葉恋歌「激動の二十八年、額田王はいかに詠ったか」
松浦 利弘
22
万葉時代の天皇歌と、明治・大正・昭和・平成の時代における四人の天皇の和歌(漢詩)
松江 信一
6
「ドルメン」と呼ばれた古墳
松田 圭悟
22
「いばら神」考察 何故、足神さんがいばら神なのか
松村 冨子
7
奈良阪逍遥
み
水永 八十生
15
大東市域の戦歿者墓石と慰霊の変化
湊 一裕
15
井路と河内の香る水
南 光弘
9
「壬申の乱」を解き明かすいま一つの視点―「太陽の道」「新羅の道」の上に立つ『斎宮』―
南 光弘
11
河内の古代氏族と渡来人-市内の式内社、新撰姓氏録から考える-
南 光弘
12
古代における聖と賤 -貴賤から浄穢へ-
南 光弘
14
ニギハヤヒ序 -郷土のニギハヤヒ伝承・神話から考える-
南 光弘
16
天武天皇と持統天皇の時代-「嶋評戸籍木簡」を読む-
南 光弘
18
内行花文鏡とアマテラスの誕生。そして、伊勢神宮成立の謎
南 光弘
20
「河内潟とウォーターフロント瓜生堂物語」
南 光弘
22
日下村井上家文書『役印記』にみる近代学校教育の魁、正法寺における郷学校設立の経緯
峰本 順吉
3
柳生街道(瀧坂道)を歩く
三村 正臣
1
石地蔵伝承あれこれ
三村 正臣
2
私の化粧地蔵散歩(茨木・高槻編)
三村 正臣
3
大阪中部の石仏概況(河内・大阪・堺)―河内の石仏所在目録編集を終えて―
三村 正臣
4
化粧地蔵探訪記―若狭・小浜編―
三村 正臣
5
五百羅漢探訪記―北伊勢菰野町竹成―
三村 正臣
6
心のかたち ~石の百面相~
三村 正臣
7
心のかたち ~石の百面相~2
三村 正臣
8
心のかたち ~石の百面相~3
三村 正臣
9
心のかたち ~石の百面相~4
三村 正臣
10
心のかたち ~石の百面相~5
三村 正臣
11
心のかたち ~石の百面相~6
宮村 和子(他一名)
1
「五十村峠」について
む
村田 隆志
4
慈雲尊者と柳澤候
も
森本 すみ子
5
道昭(道照)和尚
や行
執筆者名
号数
目 次
や
籔田 和子
11
民話 河内の、むかし むかしばなし
薮田 武子
4
百万塔に思う
薮田 武子
7
川違之普請手伝の三田藩
山根 眞人
20
枚岡大神の春日御遷幸ルートについて―神護景雲二年(七六八)―
山野 隆雄
1
弥刀の地名と歴史について
山野 隆雄
3
〈東大阪文化サロン十周年記念〉丹後半島古代の旅
山野 隆雄
7
河内の馬文化について
山野 隆雄
8
河内の国の弥生の原風景
山野 隆雄
12
高僧「行基菩薩」について
山本 律郎
2
南北朝争乱 八尾の群像
よ
吉田 裕
7
大和川付け替え余話 河村瑞賢のこと―未然を考える男の話―
吉田 裕
12
浮瀬(うかむせ)物語
吉村 馨
1
郷土・河内の偉人「三田浄久」のこと
吉村 馨
2
地籍名「キソドノ墓」のこと
吉村 馨
3
史蹟「立教館」のこと
吉村 馨
10
こぼれ話・ふるさと雑感 わが邑の「観音さん」のこと
吉村 馨
11
ふるさと雑感 風雅余話
吉村 馨
12
三田浄久 年譜 並びに 柏原船沿革年表
わ行
執筆者名
号数
目 次
わ
若松 博恵
2
高橋和巳と東大阪
若松 博恵
3
枚岡の伝説「神武東征と梶無神社」考
若松 博恵
4
ニコライ・ネフスキーと東大阪―その追跡の前提―
若松 博恵
8
日下の直越考
若松 博恵
10
知られざる東大阪市内の城