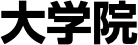公開講座・研究講座
大学院公開講座
2025年度 大阪商業大学大学院 公開講座

2025年 日本国際博覧会の社会的効果
~博覧会の開催意義と今後の展望~
本学では2022年度に「博覧会効果」と銘打ち3年後に迫った日本国際博覧会における社会的効果について公開講座を開催しました。鉄道を中心とするインフラ設備、商店街を主体とする小売業、博覧会史における大阪開催の意義という3点から登壇者が考察を加え、さらに会場からの質問を交えてシンポジウム形式で万博の開催意義と展望を論じ合いました。本年万博が開催され、様々な話題を集めましたが、はたして実際の「効果」はいかがなものであったかを論証する目的で改めて本学大学院主催のもと博覧会をテーマとした公開講座を実施します。参加者の皆様と共に万博開催の意義と今後の展望を考察していきたく、ご案内いたします。
■ 主催:大阪商業大学大学院 地域政策学研究科
| 開会 (14:00~14:20) |
◇開会挨拶◇ 谷岡 一郎(大阪商業大学 学長) ◇解題◇ 石上 敏(大阪商業大学大学院 地域政策学研究科教授) |
|---|---|
| 講演 (14:20~15:30) |
「万博の経済的波及効果をいかに「底上げ」できるか?」 加藤 司 (大阪商業大学大学院 地域政策学研究科教授) 「集客装置としての大阪万博と鉄道」 谷内 正往 (大阪商業大学 総合経営学部商学科教授) 「今回の博覧会は本当に成功だったと言えるのか」 石上 敏(大阪商業大学大学院 地域政策学研究科教授) |
| シンポジウム (15:50~16:40) |
◇パネリスト◇ 谷岡 一郎(大阪商業大学 学長) 加藤 司 (大阪商業大学大学院 地域政策学研究科教授) 谷内 正往 (大阪商業大学 総合経営学部商学科教授) ◇コーディネーター◇ 石上 敏(大阪商業大学大学院 地域政策学研究科教授) |
| 日程 | 2025年11月29日(土) 14:00~17:00(開場13:30) |
| 場所 | 大阪商業大学 蒼天ホール 大阪府東大阪市御厨栄町4-1-10 大阪商業大学へのアクセス |
| 定員 | 200名(申込み先着順) |
| 参加費 | 無料 |
| お申込み方法 |
お申込みは Web申込・E-mail・電話・FAXで受付いたします。 Web申込:https://forms.office.com/r/bUxqjUaF8j |
講師・パネリスト(講演順・敬称略)
| 講師・パネリスト | 経歴 |
|---|---|
| 谷岡 一郎 / たにおか いちろう 大阪商業大学 学長 |
1956年大阪生まれ。1997年から大阪商業大学学長。70年大阪万博には中学生の時に何度も通った。特に印象が深かったのは、オランダ館で、エッシャーのメタモルフォーゼⅢ(1968年の作品)を初めて見て、その前で一時間以上いたことを覚えている。 |
|
加藤 司 / かとう つかさ |
1959年生まれ。 東北の片田舎で育った私にとって、万博はまったく無縁の存在だった。当然、70年大阪万博にも行っていない。だが、今回だけはどうしても訪れたいパビリオンがあった。イタリア館である。しかしイタリア館は一番人気で、私が行った日には8時間も並ぶ人がいて入館をあきらめた。 私の専門はイタリア経済そのものではないが、商業や製造業による地域経済の活性化を考える上で、「国滅びて、地方都市栄える」とも言われるイタリアは示唆に富んでいる。今回の万博は大阪経済再生の起爆剤となり得るのか。地域や地方が再生していくためには何が必要なのか。万博を通して、あらためて考える機会としたい。 |
| 谷内 正往 / たにうち まさゆき 大阪商業大学 総合経営学部商学科教授 |
1965年兵庫県生まれなので、70年大阪万博はリアルタイムでは見ていない。今年の大阪万博は夜間を中心に何度か見に行き、円形リングに感動し、ドローンショー、コモンズを中心に各国のパビリオンを楽しんだ。 私の専門は商業史で、大阪の鉄道と経営者、地域、商業施設(遊園地含む)の関係を歴史的に研究している。今回は集客装置としての万博を、鉄道事業の兼業との関係で見つめていきたい。 主要業績としては『戦前大阪の鉄道とデパート』(東方出版、2014年、鉄道史学会第6回住田奨励賞)、『日本の百貨店史』(加藤論と共著、日本経済評論社、2018年)などがある。 |
| 石上 敏 / いしがみ さとし 大阪商業大学大学院 地域政策学研究科 教授 |
静岡県に住んでいた小学生の頃70年大阪万博に2回入場して以来の万博マニアとして、博覧会資料の収集にいそしんできた。とはいえその後の沖縄海洋博もつくば科学博も花博も愛・地球博も訪れる機会がなく、ただただ資料や書籍を通して学び、楽しんできた。 今回目と鼻の先で万博が開催されたことに心躍りを抑えつつ、仕事の合間に会場を訪れては、ひたすら「よかったこと・よくなかったこと」の両面を観察し、ノートに取り続けてきた。来場25回、ノート30冊の蓄積の中から、「いいこと」だけでも、「悪いこと」だけでもない万博の姿について問題提起をし、考察を続けていきたいと考えている。 |